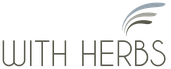【野草を食べる】ナズナ(ペンペングサ)の効果効能 利用法 解熱作用・眼精疲労・動脈硬化予防に
春の七草のひとつとして知られ、別名「ぺんぺん草」ともいわれている「ナズナ」。
日本全国の田畑、野原、空き地などいたるところにみられる野草ですが、食べると、解熱作用や眼精疲労・動脈硬化の予防などに効果が期待でき、古くから生薬として民間療法に利用されてきました。

目次
「ナズナ」とは?
エピソード
邪気を払い、万病を遠ざける薬草として、七草粥にも加えられるナズナ。
(春の七草:ナズナ、セリ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ)
その実の形からヨーロッパでは「Shepherd’s purse(羊飼いの財布)」と呼ばれています。
薬効も高いため、昔から中国では止血剤、ヨーロッパでは痛風や赤痢などの薬として使われてきました。
特徴
道ばた、人家の庭などいたるところにみられる1年草で、花は年を越して1年中咲き、草丈10~40㎝ほどです。
早春に地面にはりついたギザギザの葉から茎が直立し、茎全体に毛が生えています。
茎の先に柄のある白色で小さい花を多数つけ、果実の形が三味線のばちに似ているため、「ぺんぺん草」の別名があります。
春の七草のひとつとして知られていますが、昔は野菜として扱われ普通に食べられていました。
| 科名 | Capsella bursa pastoris |
| 科名属名 | アブラナ科・ナズナ属 |
| 別名 | ペンペングサ、三味線草、Shepherd’s purse |
| 原産地 | 中国 |
| 利用法 | 薬用、食用、茶用 |
| いつ摘める? | 若葉は2~4月、花は2~6月 |
| 生薬名 | 薺 |

ナズナの効果効能
| 主な成分 | アセチルコリン、ブルミン酸、サポニン、シトステロール、チラミン、コリン、フマル酸、アミノアルコール、フラボノイド、ヒスタミン |
| 主な作用 | 殺菌、抗菌、止血、血液循環促進、利尿、収斂、血液低下、解熱作用、消炎 |
- 下痢や便秘の改善
- 風邪の予防改善
- 目の充血などの眼精疲労の改善
- 膀胱炎・尿道炎の改善
- 肝炎の予防
- 産後における出血、月経過多といった症状の改善(妊娠中の方は分娩を除いて使用を控える方が良い)
- 動脈硬化や高血圧などの生活習慣病の予防
利用法
春に全草を採り水洗いし、2~3日天日干しにする。
高血圧や便秘、子宮出血には1日量5~10gをコップ1杯強の水が半量になるまで煎じ、毎食後3回に分けて飲むと良いです。
動脈硬化の予防には、若葉を青汁にして飲むほか、おひたしなどの料理に普通に使うことができます。
目の充血には、10gを200mlの水で煎じ、こした汁を人肌に冷まし、脱脂綿に浸して洗眼すると効果があるといわれています。
参考引用文献:100種類の見分け方・採取法・利用法 身近な薬草活用手帖
おいしい食べ方
花の咲く前の若葉は、さっとゆでて水にさらしておひたしに。
花が咲いたら全草つかってお茶に。
花だけ摘んでサラダにしてもよいです。
生食可能です。

ナズナ茶の作り方
【材料】
| ナズナ | 5~6本 |
| 水 | 1000ml |
- ナズナは花の咲いている時期に30㎝ほどの長さに切り、よく洗い水けをふく。ざるの上に置くか、束ねてつるすかして日陰で3日間ほど干す。
- 土瓶に1と分量の水を入れ5分ほど煮出す。
干さずに、そのまま急須にお湯とともに入れてハーブティーのようにしても飲めます。
ただし、生の葉の青くさい匂いや味はします。
参考引用文献:食べる野草図鑑 岡田恭子著
参考引用文献:100種類の見分け方・採取法・利用法 身近な薬草活用手帖 寺島進監修 食べる野草図鑑 岡田恭子著
※ここに掲載されている内容は専門書などを参考に取りまとめた情報です。植物の効果効能、心身の不調改善を保証するものではありません。あくまでも自己責任において使用をお願いいたします。使用に不安のある方は専門家や専門医に相談することをお勧めいたします。妊娠中、授乳中、小さな子ども、持病がある方、その他心配なことがある方は注意が必要です。