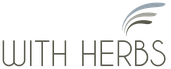【野草を食べる】トウキ(当帰)の効果効能 利用法 育て方 女性特有の悩みに 薬に頼らず健康に
線香花火のようなかわいらしい花と独特の甘い香りが特徴の「トウキ」。
ここでは、婦人病の特効薬として古くから利用されている、トウキの薬効、利用法、食べ方をご紹介しています。

目次
トウキ(当帰)とは?
独特な甘い芳香があり、茎は直立して草丈が30~90センチになる多年草のトウキ。
本州の山地の岩場、がけなどで自生、または薬用植物として各地で栽培されています。
葉はセリの葉に似ており、茎と葉柄(ようへい)は赤紫色を帯びていて、葉は3つに分かれています。
8~9月ころに花茎を出して多数の小白花をから傘状(複散形花序)につけ、果実は長さ5~6ミリの長楕円形です。
根は太く枝分かれし、ひげ根も多くて香りもあるため、よく朝鮮人参と間違われます。
根は当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)、当帰建中湯(とうきけんちゅうとう)の漢方薬に配合されています。
| 学名 | Angelica acutiloba |
| 科名 | セリ科 |
| 生薬名 | 当帰(トウキ) |
| 別名 | オオゼリ、乾帰(カンキ)、カマゼリ |
| 利用部位 | 根、葉、茎、花 |
| 利用形態 | 薬用、食用、浴用 |
採取時期
葉は8~9月の開花時に刈り取り、2~3日日陰干しして保存しておきます。
根は11月ごろに堀り、水洗いして天日干しにするか、半乾燥のときに湯揉みして天日干しにする。
薬効と使用方法
婦人科の妙薬(当帰)
1日5~10g煎じて服用するか、お風呂に入れれば造血能力を強くし、血を補い、血液を浄化して産前産後、妊婦の腹痛や出血、血の道、月経不順、不妊症、更年期障害に効果があります。
妊娠中、授乳中以外は酒で服用しても良いでしょう。
また、風邪、咳、頭痛、めまい、動悸、肩こり、虚労(病気による疲労)、中風、神経衰弱、ヒステリー、腺病質、貧血、浮腫、腎炎、冷え性、しもやけ、痔に効果があります。
茎葉を用いても良いでしょう。
ひび、しもやけ(浴湯料)
当帰の煎液をしばしば患部に塗布するか、風呂に入れれば効果があります。

おすすめの食べ方(葉、茎、花)
トウキ餃子
トウキを刻んでひき肉と一緒に混ぜ合わせ、餃子にするととてもおいしいです。ニラの代わりになります。
刻んだトウキは、かき揚げやお好み焼きに入れても美味しくいただけます。
薬草カレー
その時期に手に入る薬草をカレーに入れると簡単に薬草の栄養素を取り入れることができます。
多少硬いものでも薄く刻めば入れることができます。
コツは油をたくさんに入れ、十分に炒めると良いでしょう。
トウキ酒
10月頃に採取した果実を用います。
果実の4、5倍量のホワイトリカーをいれ、砂糖を果実の3分の1程度をいれて、1~2ヶ月くらい漬け込んだ後いただきましょう。
生薬の当帰(とうき)も同様にトウキ酒にすることができます。
便秘に効果があるといわれています。
トウキ茶もおすすめ
宮崎県高千穂町の無農薬栽培の日向当帰茶。
お手軽にトウキと取り入れることができおすすめです。
専用スプーン1杯~2杯を湯呑みに入れお湯を120ml~150ml注いでお召しあがり下さい。
参考引用文献:大地の薬箱 食べる薬草事典 春夏秋冬・身近な草木75種 村上光太郎著
※ここに掲載されている内容は専門書などを参考に取りまとめた情報です。植物の効果効能、心身の不調改善を保証するものではありません。あくまでも自己責任において使用をお願いいたします。使用に不安のある方は専門家や専門医に相談することをお勧めいたします。妊娠中、授乳中、小さな子ども、持病がある方、その他心配なことがある方は注意が必要です。多量の摂取するのはやめましょう。