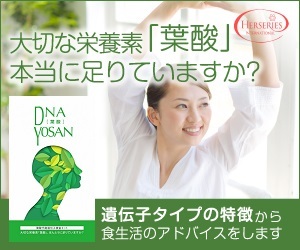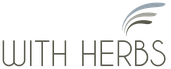【野草を食べる】ドングリの効果効能 非常食として デトックス効果あり
子どものころ夢中になってひろった「ドングリ」。
コマなどのおもちゃにして遊んだことことはあっても、食べたことのある人は少ないのではないでしょうか?
実は、栄養価が高く体内に蓄積された有害物質の排出を促すデトックス効果もあり、縄文時代は主食にしていたようです。

目次
ドングリとは?
ドングリとはブナ科の果実であるマテバシイやクヌギ、スダジイなどの総称です。日本には約20種類のドングリの木があるといわれています。
種子の大部分はデンプン質で、縄文時代は主食として食べられていました。
お米が主食になってからも、ドングリは飢餓や食糧難に備える非常食とされ、神社に植えられることが多かったそうです。
「団栗の背比べ」といいますが、あれは同じ種類のドングリを背比べしてもほぼ同じなので、それから来た言葉だといわれています。「団」は「まるい」という意味を持ち、団栗は「丸い栗」という意味であるように、味は栗に似ています。
| 英名 | acorn |
| 科名 | ブナ科 |
| いつ摘める? | 9~11月ごろ落ちているものを拾う |
| どこで? | 日本全国の道ばたや野原、山林など |
| 摘み方 | 落ちているものを拾う。木になっている実は熟していないため渋く、地面に落ちた実は完熟していておいしい |
| 注意 | 殻を割ると虫が出てくることがあります。 |

ドングリの効果効能
| 主要成分 | アミノ酸、ビタミンA、ビタミンCなど |
| 期待できる効果 | 殺菌、解毒、デトックス効果など |
ドングリは68%が炭水化物、18%が脂肪、6%がタンパク質で、アミノ酸、ビタミンA、ビタミンCなどの栄養成分を含んでいます。ドングリの渋みはタンニンやサポニンであり、渋みが強いものもあるため、アク抜きなどの下処理をしてから料理すると良いでしょう。(参考サイト・『JA長野県』)
ドングリには体内に蓄積された重金属などの有害物質の排出を促すデトックス効果があるといわれています。
また、殺菌や解毒といった効果もあり、含まれる繊維質と合わせて快便効果もあります。
さらに殺菌作用があるため、風邪予防にも効果が期待できます。
ドングリの葉や枝には体内にできた結石を溶かす効果のある成分が含まれています。
お茶として取り入れると良いでしょう。
おいしい食べ方
「ドングリ」のアクの抜き方
ドングリは種類によっては渋みが強いものもあるため、アク抜きなどの下処理をしてから料理すると良いでしょう。
拾ってきたドングリの殻をペンチなどで割り薄皮をはがします。
上手くできないときは、厚手のフライパンで炒って殻がはじけてから中の実を取り出したり、1週間ほど天日干しにしていると殻が割れるものもあります。
中の実を取り出したら、水に1時間ほどつけておくとアクが抜けます。
短時間でアクを抜きたいときには、沸騰させたお湯で10分ほどゆでます。ゆでたらザルにあげて、水洗いをして水気を切ります。
「煎りドングリ」の作り方
アクのすくない椎の実などのどんぐりは、フライパンで炒る方法で食べることができます。
| 材料(作りやすい分量) | |
| ドングリ(マテバシイやスダジイなどの椎の実) | 好みの分量 |
- ドングリとフライパンに入れて、ふたをしながら炒る。
- パンパンと音がして、はぜてきたら出来上がり。焦げ目がつくくらいでいい。すぐに中の実を取り出してから食べる。熱いうちが柔らかくておいしい。殻をむくときはペンチを使うといい。

「玄米ドングリお赤飯」の作り方
栗ごはんと同じようなほっくりした味です。
| 材料(4人分) | |
| ドングリ(殻付き・マテバシイの実) | 300g |
| 玄米もち米 | 2カップ |
| 小豆 | 25ml |
| 水 | 430ml |
| 塩 | 少々 |
- ドングリをフライパンに入れて、ふたをしながら煎る。
- パンパンと音がして、はぜてきたら出来上がり。焦げ目がつくくらいでいい。すぐに中の実を取り出す。熱いうちでないとかたくて殻がむけない。ペンチを使ってもいい。
- 圧力なべに、すべての材料を入れ30分弱火にかける。強火にし、重りが回りだしたら、ごく弱火にして20分炊く。ふたを開けてしゃもじで上下に返す。
参考引用文献:食べる野草図鑑 岡田恭子著
※ここに掲載されている内容は専門書などを参考に取りまとめた情報です。植物の効果効能、心身の不調改善を保証するものではありません。あくまでも自己責任において使用をお願いいたします。使用に不安のある方は専門家や専門医に相談することをお勧めいたします。妊娠中、授乳中、小さな子ども、持病がある方、その他心配なことがある方は注意が必要です。多量の摂取するのはやめましょう。