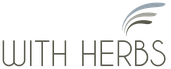薬草と人の歴史
太古の昔から人々は病気になると身の回りにある薬草(緑の薬)で自らを癒してきた歴史があります。
やがて化学合成薬品(白の薬)が登場したことで、植物による治療は歴史の表舞台から姿を消すことになりますが、近代を過ぎたあたりから再び脚光をあび現在に至ります。
今回は、薬草と人の歴史をご紹介します。

目次
薬草魔女
植物は薬のない時代から人々の健康を支えてきました。
そんな中薬草の知識にたけ、野山や庭で薬草を摘みその薬効で人々を助けていた女たちがいました。
彼女たちは「賢い女」と呼ばれ、人々に重宝されていました。
それがいわゆる「薬草魔女」なのです。
彼女たちは直感に秀で、自然を敬うことによって自然から知恵や恵みを授かっており、薬草に宿る神々と病人との間をつなぐメディアと自らを位置づけてシャーマニスティック(呪術的)な治療を施していました。
その後、歴史の表舞台から姿を消すことになりますが、現在でも先住民の文化では引き継がれています。

古代ギリシャの医師「ピポクラス」
直感を重視した時代に続き、古代ギリシャの医師ピポクラス(BC460~377)は迷信に頼らず科学的根拠に基づいた医学を確立しました。
彼の薬草治療は、病気は体液のバランスの乱れから生じると考える「体液病理説」により、267種類の薬草を用いた記録が残っています。
また、ピポクラスの知的後継者であるテオフラストス(BC372~287)は「植物の父」と言われ、「植物誌(Historia Plantarum)」には約500種の植物の記録があります。
その後ギリシア・ローマ医学は中東にもたらされ、アラビア医学と合流し、インド伝統医学(アーユルヴェーダ)も加味され、ユナニ医学となり現在のパキスタンやインドで実践されています。
ユナニ医学の大成者としては、精油の蒸留法を確立したイブン・シーナ(アヴィセンナ/980~1037)が知られています。

修道院医学
アラビア医学はユナニ医学への流れとは別に再び欧州に伝えられ、修道院医学として確立されていきました。
修道院は、周辺の貧しい人々や旅人にとって宿泊可能な病院のような存在で、臨床医学の実践の場でもありました。
中世ドイツの女子修道院長ビンゲンのヒルデガイド(1098~1179)の書物には、体液病理説に基づいてカモミールやラベンダーなど多様なハーブが登場します。
修道院医学の主な柱はフィトセラピ・薬用植物療法で、修道院関係者の薬草・薬であったハーブやスパイスについての知識は今も大学の研究者を驚かせています。
その当時、古代ギリシャの医師ヒポクラテスの教えも、翻訳され、中世ドイツを含めて、修道院医療関係者にヨーロッパで広く使われていました。
収穫したハーブを乾燥させたり、植物油に漬け込み成分を溶出させるなど、保存法や調整法がこの時代に進歩し、薬草加工室や薬剤保管室などの設備が整うことで、のちの薬局の原型が誕生したと言われています。

大航海時代・東西交易
アラビア医学では、アッタールという薬種商が、ハーブやスパイスを扱い、グローブやコショウなどの交易を独占したことで莫大な富を築きました。
一方イタリアのクリストファー・コロンブスは東方のジパングを目指し、1492年に偶然、新大陸に漂着します。
これを機に15世紀から17世紀にかけ大航海時代が到来し、新大陸からはジャガイモやトマト、それに先住民であるインディオたちの医学に用いられていたエキナセアやコカの葉などがヨーロッパにもたらされました。
東西交易により遠く離れた地の薬草も人々に利用されるようになり、持ち込まれたハーブやスパイスを活かして研究がさらに進められました。
日本でも16世紀にはスペインやポルトガルの宣教師が来日し、ピポクラス医学を源流とするオランダ医学やドイツ医学が伝えられました。

化学合成薬時代が到来
19世紀に入ると、天然物化学の発展によりハーブから活性成分の単離や合成が進み、1805年にはアヘンからモルヒネ、1860年にはコカの葉からコカインが単離され、1897年にはアスピリンが合成されます。
1928年にはフレミングがペニシリンを発見し抗生物質の時代がはじまります。
そして、19世紀後半には次々と細菌が発見され「特定病因論(特定の病気は特定の菌によってもたらせるという考え)」が世の中に定着しました。
医療のために植物全体を使うのではなく、植物から化学物質を取り出して利用する方法が進み、やがて化学物質を合成する研究も進み、医薬品と言えば製薬会社が作るのが一般的になりました。
緑の薬(薬草)は白の薬(化学合成薬品)にその座を受け渡すこととなり、植物療法は徐々に衰退していきます。

自然回帰へ
ペニシリンに代表される抗生物質は、あたかも魔法のように病魔に打ち克つことから「魔法の弾丸」と称されました。
しかし20世紀の中頃を過ぎると「魔法の弾丸」が威力を発揮する感染症から、生活習慣病や心身症など病名の無い不調を訴える人が増加します。そのため、病気になる原因を予防するという考えが広がっていきました。
また、時を同じくして薬害や副作用などの問題が一挙にあらわれました。
そこで人々は行き過ぎた科学万能主義を反省し、アメリカ西海岸発の自然回帰運動は若者を中心に世界中に広がりました。

薬草とこれからの医療
野菜や果物といった食材に病気を予防する機能があることを1980年に世界に先駆けて調査研究したのは、ほかならぬ日本でした。
古くからある医食同源というコンセプトが科学的に正しいことが実証され、植物療法の知識が食生活におおいに役立つようになりつつあります。
また、植物療法による五感の刺激は、生命力を賦活し生活の質を高めてくれるため、病気を予防に期待ができます。
さらに今日では医薬品・手術・放射線を武器とする近代・西洋医学と、植物療法・音楽療法などの相補・代替療法のいずれも視野にいれ、患者さん中心の医療を目指す総合医療が欧米で普及し、日本でもその取り組みがはじまっています。
統合医療とは決して反西洋医療ではありません。
統合医療は複数の療法を組み合わせることが良くあり、臨床現場では医師やセラピストなどがチームを組んで、広い知識と専門性をいかし患者さんを支えることになるようです。
参考引用文献:ハーブと精油の基本事典 林真一郎著、ハーブのすべてがわかる事典 ジャパンハーブソサエティー著

※ここに掲載されている内容は専門書などを参考に取りまとめた情報です。植物の効果効能、心身の不調改善を保証するものではありません。あくまでも自己責任において使用をお願いいたします。使用に不安のある方は専門家や専門医に相談することをお勧めいたします。妊娠中、授乳中、小さな子ども、持病がある方、その他心配なことがある方は注意が必要です。